法要と法事の上手な断り方とは?最後は檀家を辞める覚悟で!
 「法要と法事を上手に断りたい」と悩んでいませんか?菩提寺の僧侶は老練で言葉巧みに法要を強いてきます。いつの間にか初七日・四十九日・百か日・初盆・一周忌・三回忌と立て板に水のごとく僧侶の口から日程を進められます。法要や法事を断りたいときに、僧侶との話は「離檀覚悟」の交渉も。
「法要と法事を上手に断りたい」と悩んでいませんか?菩提寺の僧侶は老練で言葉巧みに法要を強いてきます。いつの間にか初七日・四十九日・百か日・初盆・一周忌・三回忌と立て板に水のごとく僧侶の口から日程を進められます。法要や法事を断りたいときに、僧侶との話は「離檀覚悟」の交渉も。
葬儀後の僧侶の法要の上手な断り方
父親が亡くなり、葬儀に僧侶から法要の説明があったようです。
私の場合は、コロナ緊急事態宣言で葬儀に参列できませんでしたので、田舎に住む長女夫妻(姉)が声を上げてくれて無事葬儀は終了しました。
父親の急死で、姉は気が動転していたと思います。
誰しも身内の葬儀に立ち会うのは、そう多くはなく、数少ないのが当たり前です。
片や、毎日が「葬儀」「法要」「法事」という仕事をしている菩提寺の僧侶。
葬儀の出だしから、僧侶にお世話になってしまうため、どうしても主導権はお寺さん(住職)に委ねられてしまいます。
都会では、初七日、四十九日は、葬儀が終わって火葬に入る前に法事を行なって省略しています。
ところが、地方はまだ法要や法事を事細かに、僧侶の言うがままに受け入れています。
どうしても、法要や法事を省略したいときに、住職に上手に断る方法を紹介します。
まず最初は毎月の法要だけ断る
お坊さんと言えども人間です。
僧侶とトラブルような話し方は、すべきではありません。
何故だか僧侶や住職といった、異次元の世界の人と喧嘩になったりすると怖い気がしませんか。
一応、法要をお断りするというお願いごとですよね。
僧侶にとって、大きな収入減とならないものから、少しずつお断りをするというのが礼儀です。
- 毎月の法要を辞める
- 年に1~2度の命日やお盆だけお願いする
菩提寺の住職やお坊さんの言うとおりに法要や法事をやっていたら、時間も予算も無制限にかかってしまいます。
法要はお坊さんや住職さんたちの仕事なのです。
法要や法事の説明では、やって当然という考え方で説明されます。
法要や法事の断る理由は?
菩提寺の住職に法要や法事を断る理由が必要です。
直接、面と向かって住職にお断りが言えないときは、電話でもいいです。
その時の断る理由が大事な訳です。
住職に法要を断る理由を聞かれたときは、
- 今の仕事が大変で、休みが思うように取れない
- 家族の者が体調を悪くしている
- 母親が痴呆で施設と家の介護で大変
- 金銭的な問題の場合は正直に説明
お寺さん側の事情
お寺さん側も法要で生計を立てているわけですので、そう簡単には受け入れてくれません。
菩提寺も檀家さんが少なくなってきていて、強気の姿勢ばかりではうまくいかないところも・・・。
それでも、強気のお寺さんはあります。
最後の切り札を出すお寺さん。
私の場合ですが、最後の切り札「檀家をやめる」「檀家を抜ける」というお話がありました。
お寺さんが出す最後の切り札「檀家を抜ける」
父親が亡くなり、葬儀が終わり、さらに四十九日が終わった後に、納骨堂の件で和尚さんからお話がありました。
- 新しく納骨堂を建設したので、父親の他界と同時に新しい納骨堂の購入を勧められました。
購入費用 60万円 毎年の維持費用13,000円が必要 - 永代供養を申し込む件についても
永代供養料 100万円 毎年の維持費用は不要
お寺が存在する限り供養してもらえる - 檀家を抜ける
現在、預けている遺骨を引き取る
離檀料 30万円
今後、菩提寺とのお付き合をどうするかのときに、住職が示してきたお寺さんとのお付き合い方ということです。
宗教に関する考え方になりますので、費用面での高いとか安いとかは別にします。
法要や法事だけでなく、いろいろな手段でお寺さんは檀家に年貢を納めさせる方法を編み出します。
現在、先祖が購入した納骨堂は古くなっていることは事実です。
だからと言って、新しい納骨堂を購入しないと「離檀」になるとは??
檀家を辞めるとなると、何かと大変な作業がついてきます。
先祖代々のお墓の場合、自分の親や祖父だけでなく、名前すら知らない先祖様のお骨も新たな場所へ引っ越すことになります。
檀家を抜けるということは、最後の最後の手段ということになります。
お寺さんは、「檀家を抜ける」ということばで、巧みに話の天秤を重くしたり、軽くしたりしてきます。
コロナ問題で、日本中が活きるか、今後の生活でどう生きるか苦しんでいるというのに、永代供養料100万円とは?
お寺さんというのは、浮世離れしているとでもいいましょうか。
法要や法事を上手く断れない人に
本山納骨という方法が西日本では古くから行われています。
宗派の本山で安心感が高い
一番の特徴は宗派の本山で供養してもらえるという安心感があります。
本山ですので寺院の今後の運営に信頼がおけます。
宗派は問われない、戒名は不要。
納骨の費用が安い
通常価格は2万円~10万円、基本的に年間管理料や寄付などはありません。
法要と法事の上手な断り方とは?まとめ
菩提寺の住職さんとの話し合いですので、誠意をもって接すれば頷いていただけると思いますよ。
毎月の法要など、お寺さんの収益に大きく影響しないものから少しづつお断りしていく。
最終的には、本山納骨ということもできます。
時代とともにお寺さんや遺骨に対する考えは、変化しているのは確かです。
火葬場に来る人も以前と比べて、少なくなりました。
葬儀も家族葬的なものに変わり、社葬といった大勢が参列する葬儀はほとんどありません。
特に記憶に残っている火葬が、お一人の御婦人が棺に赤いバラを1本だけ捧げて最後のお別れ。
そして、収骨した骨壺を葬儀社の宅配に頼んで、タクシーで帰られました。
僧侶も誰もいらっしゃいませんでした。
後でわかったことですが、
長年、介護施設で生活されていたお父様を見送られたということです。
最後は、バラの花1本でいいですよね。
法要や法事を忙しくやる必要は??・・・。





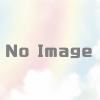



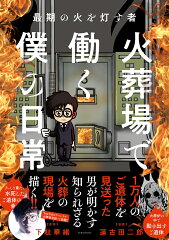
 ブログの管理人(kandume)からのごあいさつ。
ブログの管理人(kandume)からのごあいさつ。












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません